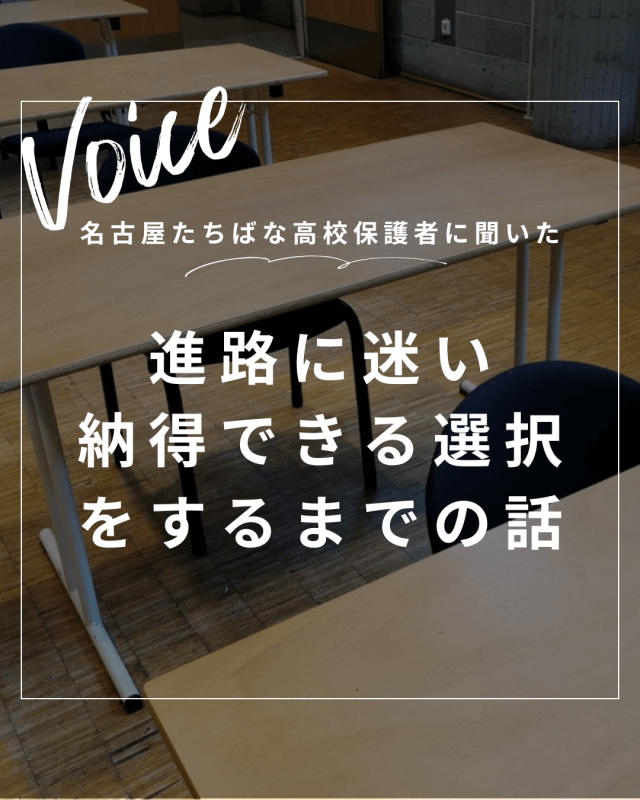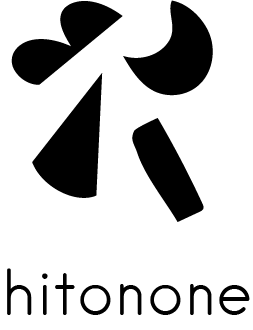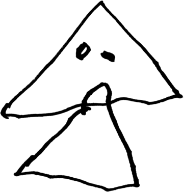2025.03.19
進路選択は“経験”と“対話”──名古屋たちばな高校1年生の母が語る、息子の成長と進路決定
こんにちは。
今回は、愛知県の私立高校(名古屋たちばな高校)に通う高校1年生の息子さんと、清流特別支援学校を卒業後、社会人になったお兄さんを持つお母さんにお話を伺いました。
中学校卒業後の進路選択で、たくさんの選択肢を見ながら、じっくりと進路を決めた息子さん。現在は毎日、自転車と電車を使って元気に通学しています。
進路を決めるまでの過程や、子どもの成長を感じた瞬間について、お話を伺いました。
自分で登校する姿に成長を実感
高校生活が始まってから、毎日自転車と電車を使って通学しています。
以前、一緒に学校まで行ったとき、電車内でのマナーがしっかり身についているのを見て驚きました。周囲を気にしながら行動できていて、『ちゃんと成長しているんだな』と実感しましたね。
こうした経験を積み重ねることで、本人の中に“できること”が増えていっているんだと思います。
進路選択は慎重に。たくさんの選択肢を見ることから始めた
兄の時、学校から「清流特別支援学校が合うのでは?」という提案がありました。
特別支援学校を卒業しても「高卒」にならないこともあり、選択は慎重に考えていたので、その後の進路の幅も考え、たくさんの学校を見学しました。
弟の場合は、清流特別支援学校ではそもそも合わないと感じていました。どこならフィットするのか、県内外の公立・私立を含めて情報を集めました。
“対話”を大切にした進路決定のプロセス
子どもたちは、最初は親に引っ張られる形で進路を考え始めました。でも、たくさんの学校を見て話をするうちに、自分ごととして考えるようになったと思います。
やりたいことや、各学校でできることを整理し、表にして可視化。「ここではこんなことができる」「これは難しそう」と、具体的に話をしました。
ただ選択肢を増やすだけでなく、それについて話し、本人の思いを聞く機会を多く作ることが大切だったと感じています。最終的には、本人が納得して選ぶことが何より重要ですね。
“やりたいことがない”時期の不安と、今の姿
小さい頃は好きなことをとことんやる子でした。でも、中学生になると、それがなくなってしまって、少し心配していました。学習面では、集中力が続かない、テストを最後までやりきれないなどの課題もありました。
高校に入ってからは、工業高校ならではの学びに楽しさを感じているようです。もともと数学が好きだったので、製図や工業数学に興味を持ち、前向きに取り組めています。
“できること”を増やすために、小学生のうちから意識したこと
生活の基盤を整えることが最優先だと考えていました。
勉強の遅れは気になる部分もありましたが、それ以上に、生活習慣を整えたり、できることを増やしておくことが大切だと思いました。
例えば、小学生のうちから一人で電車に乗る練習をする、ご飯を炊くなどの生活スキルを身につけるようにしていました。
中高生になると、勉強や部活などで忙しくなります。だからこそ、小学生のうちにある程度の基盤を作っておくことで、スムーズに成長できるのではないかと感じています。
まとめ:進路選択は“経験”と“対話”がカギ
進路選択は、親が決めるものではなく、本人が納得して決めるもの。そのためには、たくさんの学校を見ること、話すこと、情報を整理することが大切だと思いました。
また、進路選択の過程で、生活スキルや自己管理能力も少しずつ身についていきます。
「高校はどこにするか」だけでなく、その先のことを見据えながら、子どもと一緒に考えていくことが大切なんだと改めて感じています。
お母さんのお話から、「進路を選ぶ過程」そのものが、子どもにとっての大きな成長の機会になることが伝わってきました。
進路選択に迷う時期は、不安も大きいもの。でも、“対話”と“経験”を積み重ねることで、子ども自身が納得できる道を見つけることができるのかもしれません。
そして、お母さん自身が前向きな考えでいられるのは、「自分の時間を大切にしているから」とのこと。進路を一緒に考え、支える中で、お母さんも好きなことをする時間を持つことが、結果的に良い関わりにつながるのかもしれません。
進路選びに悩むご家庭の参考になれば嬉しいです!