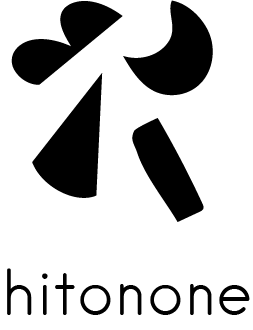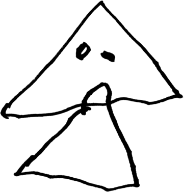2025.05.15
子どもの“サポート”って、どこまですればいいの?
思ったように動いてくれない家族に…
塾生のお母さんがぽろっとこんなことを話してくれました。
「お父さんが、持ち物の準備や学習のフォローを思ったようにしてくれなくて、なんで!!って思うこともあります」
共働きやさまざまな家庭の事情の中で、子どもの生活や学習の支援をどう分担するか。
現実には、そのことで保護者が疲れてしまったり、誰かに「わかってほしい」と感じることも少なくありません。
そもそも、子どもをどのようにサポートするのがいいと考えるかが、人によって様々。
夫婦の間でズレが生じるのは、よくあることです。
中学生だから「自分でやって当たり前」…?
中学生にもなれば、次の日の持ち物の準備や提出物の管理は「自分でやって当然」とされがち。
でも、それが難しい子もいます。
忘れ物が多い、先の予定を見通すのが苦手、気持ちの切り替えがうまくいかない――
そんな特性を持つ子にとっては、「自分でやる」のハードルがとても高いこともあるのです。
「どこまで手を出す?」に正解はない
「親がやってあげるのはよくないのでは?」
「でも手を出さなければ学校に行けなくなるかも…」
こんなふうに悩んでいる方も多いと思います。
役割分担の問題だけではなく、
「子どもにどこまで関わるか」という価値観のすり合わせも必要で、
それがすごく難しいと感じます。
考え方は様々。
いい悪いはない。
でも簡単にすれ違って、苦しくなってしまいます。
印象的だった、ある高校の先生の言葉
以前、こんな話を聞きました。
高校に進学した塾生のひとり。
お母さんが、いまだに学校の準備を手伝っていることに対し、
最初は「高校生なのに…」とモヤモヤしていたそう。
でもあるとき、先生からこう言われたそうなんです。
「“高校生なのに”と思わず、手を出していいんです。
その代わり、頑張れるところは本人に頑張らせてください」
この言葉でお母さんはふっと楽になり、
納得してサポートできるようになったそうです。
その結果、子どもも以前より前向きに学校や学習に取り組めるようになったとか。
支援の“線引き”は人それぞれ
大事なのは、「全部やる or 何もやらない」ではなく、
今、その子にとって必要なことを一緒に考えること。
家庭のかたちも、子どもの特性も、それぞれ違うから、
サポートの形も当然、違っていい。
だからこそ、面談では「どう関わればいいんだろう?」というモヤモヤを
一緒に言葉にして、整理していけたらと思っています。